憧れの臨床医から米国留学を経て基礎研究の道に
国立がん研究センターで新天地を切り拓く(後編)
武藤朋也(国立がん研究センター研究所 がんRNA研究分野 主任研究員)
2024.02.29
米国ではMDS幹細胞の増殖機序などを追究
マウス肝炎ウイルス蔓延による研究中断も乗り越え

2015年4月に妻と5歳の娘とともに米国に渡り、シンシナティ小児病院医療センターでの研究生活が始まりました。当初は3〜4年の留学のつもりでしたが、形にしたい複数のプロジェクトに携わることができたため、2020年2月まで約5年間米国に滞在し、最終的には4つの研究成果をまとめることができました。所属したラボのボス、Daniel T. Starczynowski先生は私と1歳違いで、スポーツも得意な人でした。Daniel氏はラボのメンバーのキャリアについても親身になって考えてくれる人で、こういうボスに出会えたことはとてもラッキーだったと思います。なお、米国で息子が誕生したのですが、彼のミドルネームにボスのファーストネームの“Daniel”の名をつけたところ、ボスはとても喜んでくれました。
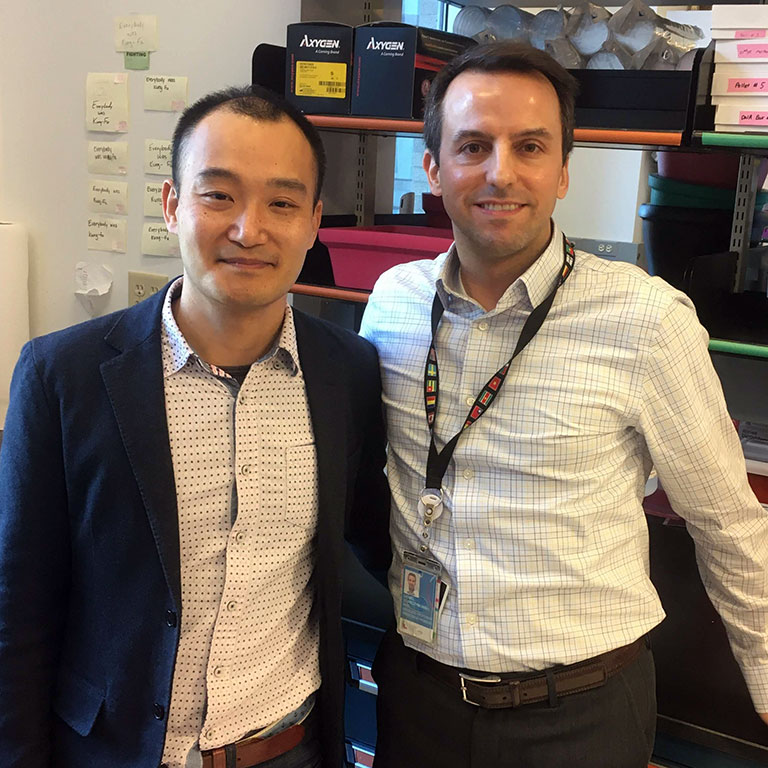
ラボの研究テーマは造血器腫瘍病態における自然免疫シグナルの役割でした。具体的には、MDS細胞の正常造血に対する増殖優位性と炎症の関係について研究に取り組みました。自然免疫シグナル活性化において中心的役割を担っているTRAF6を血液細胞特異的に高発現しているトランスジェニックマウスを用いて、トル様受容体4のリガンドであるリポポリサッカライド(LPS)を用いて慢性炎症を誘導した結果、細胞外因性の炎症と細胞内因性の自然免疫シグナル活性化の協調作用により、MDS幹前駆細胞が正常造血に対する増殖優位性を獲得していることを証明しました。そのメカニズムにおいて、MDS細胞はA20を介したnon-canonical NF-κB経路の活性化という特有の炎症性微小環境に対する反応性を獲得していることも明らかになりました。一方、正常造血幹前駆細胞は、canonical NF-κB経路活性化により機能低下が引き起こされていることから、炎症に対する反応性の違いが、MDS細胞の骨髄内増殖優位性の獲得に重要な役割を果たしていると考えられました。さらに、A20やnon-canonical NF-κB経路が新たな治療標的となり得ることも示唆されました。

ところがこの研究を進める中で、施設内でマウス肝炎ウイルスの感染が拡がってしまいました。マウスのクリーン化からやり直すことになり、この研究が元の状態に戻るまで1年半を要しましたが、帰国3カ月前に『Nat Immunol』に何とか論文投稿できました。厳しいことで知られる査読者から非常に好意的なコメントをもらい、初回投稿からわずか2カ月で受理され、2022年に「Adaptive response to inflammation contributes to sustained myelopoiesis and confers a competitive advantage in myelodysplastic syndrome HSCs」のタイトルで掲載されました。途中で実験を投げ出さなかったことが最後の大逆転そして論文化につながったわけで、苦しいときでもそのときにできることを粛々と進める重要さを実感しました。
マウスの実験ができない期間は、他のプロジェクトに打ち込みました。最も注力したプロジェクトは、TRAF6とCHIP関連遺伝子変異であるTET2欠損骨髄細胞の関連を調べる研究です。その結果、TET2欠損骨髄細胞でTRAF6が低下することで急性骨髄性白血病(AML)を引き起こすことを見出しました。その分子メカニズムは、核内TRAF6がMYCのK148をユビキチン化することで修飾部位のアセチル化を競合的に阻害し、MYCタンパクの安定化非依存的に転写因子活性を抑制するというものでした。最終的にはこの研究成果も『Cell Stem Cell』誌に受理され、2022年に「TRAF6 functions as a tumor suppressor in myeloid malignancies by directly targeting MYC oncogenic activity」として掲載されました。

米国での最後の仕事は、MDSで最も高頻度に認められる染色体異常である5番染色体長腕欠失(5q−)と、MDS幹細胞の増殖機序の解明でした。研究の結果、5q−関連遺伝子欠損マウスを用いて、炎症下における5q−MDS造血幹細胞がp53発現上昇を介して機能的に枯渇することを明らかにしました。このことから、5q−MDS幹細胞が正常造血細胞に対して増殖優位性を獲得するためには、p53遺伝子変異などのイベントが必要であると考えられました。論文は帰国間際まで行なっていた実験結果をまとめたものです。帰国のタイミングが世界的な新型コロナのパンデミックの時期と重なり、日本(千葉大学)と米国の研究室との連携が難しいときもありましたが、Zoomなどを用いて実験内容を検討しながら実験を進めていきました。研究成果は『Haematologica』誌に受理され、2023年に「miR-Inactivation of p53 provides a competitive advantage to del(5q) myelodysplastic syndrome hematopoietic stem cells during inflammation」として掲載されました。
この他にも論文1本を執筆し、米国での研究で4本の論文を筆頭著者として報告しました。2019年には米国血液学会(ASH)で、Outstanding Abstract Achievement Awardを受賞しました。Daniel氏や多くのラボの仲間の協力があってこその受賞だと感謝しています。
帰国後は指導者として臨床・研究・教育に従事
基礎研究に打ち込める環境を求め国立がん研究センターへ
2020年春に帰国し、4月から千葉大学血液内科の助教として、病院での診療、医学生や大学院生の教育、研究という生活になりました。帰国前には、米国でいい仕事ができたので基礎研究を続けたいという気持ちがあり、周囲からの基礎研究の教室への所属の勧めもありました。その一方で、小さいときからの憧れだった臨床医を続けたいという思いもあり、5年間臨床を離れていた妻の復職、2人の子どもの子育てなどを考えて、千葉大に戻ることにしました。
千葉大では、炎症シグナル物質に着目した造血器腫瘍の分子基盤の解明をテーマとした研究をいくつか立ち上げ、科学研究費基盤B、白血病基金の荻村孝特別研究賞などを獲得しました。しかし、研究だけに没頭するわけにはいかず、臨床では次々に登場する新規治療について学び、それを現場で実践するという努力が求められ、臨床研究を行なうための倫理的な手続きなどにも忙殺されました。その結果、研究アイディアが浮かんでもそれを実行に移すことはできませんでした。
それまで私は、やりたいことだけでなく、やらないことも心の声に従って自分で決めてきました。そして、帰国後に最初に指導を始めた大学院生の修了を機に、臨床医の立場を退き、基礎研究の道に進むことを決めました。
とはいえ、この年齢で研究者として迎え入れてくれるアカデミアの施設は関東圏にはそれほど多くありません。一方で、臨床医である妻がフルタイム勤務しながらワンオペで子育てするのは難しく、単身赴任は選択肢になりえませんでした。岩間先生、指田先生たちにも相談する中で、吉見先生の研究室拡大に伴い、スタッフが必要になったとの情報が入りました。早速、吉見先生にお会いし、スタッフに加わることをご快諾いただきました。
千葉大の送別会では、ある先輩に「僕も君のように、研究一筋の道に進みたかった。でも臨床、教育、研究に追われるうちに機を逸した」と言われました。私はこれが最後のチャンスだったんだと思いました。
2023年4月に、国立がん研究センター研究所がんRNA研究分野の主任研究員として着任しました。3年間、手を動かしていなかったので勘を戻すのに少し時間がかかりましたが、実験マウスの準備が進み、解析に向けた基盤が整ってきました。
これまで臨床医として、造血幹細胞移植後や自己免疫性疾患などにおいて、炎症の制御異常が致命的な病態を呈する症例を経験し興味がありました。吉見先生の研究室では、炎症制御異常とRNA制御異常の理解を融合させ、造血器腫瘍だけでなく様々な悪性腫瘍を横断的に研究し、病態解明を進めていこうと考えています。